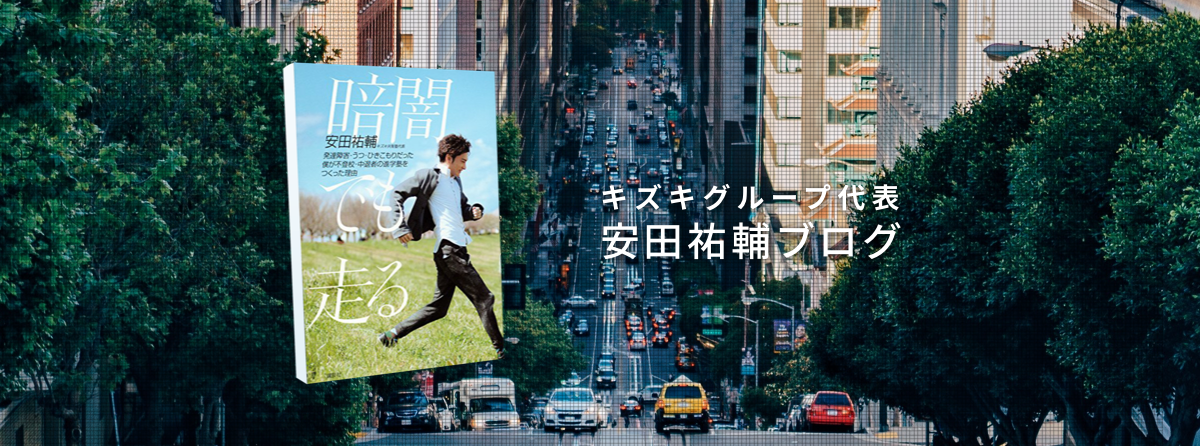コソボは居心地がよかったため、ついつい長居してしまった。 忘れないうちにコソボ事情を。 外務省の海外渡航安全情報によれば、コソボはイスラエル軍の攻撃が始まったレバノンのイスラエル国境付近と同列の扱いを受けている。退避勧告までカウントダウン、イラク一歩手前といった感じだ。 紛争が終わって7年が経った今も、まだ情勢が安定しないみたいだ。 入国する前はマケドニアで少々体を休め、コソボを前に緊張していた。 しかし入国後、そんな不安は消え去る。 予めチケットを買っておいたマケドニア発コソボ行きのバスに乗り遅れてしまい途方にくれていたところ、コソボ人のバスの運転手がアレン...
...From Kosovo
I am in Kosovo. Almost 1 week has passed sinse I came here. Here is so beutiful. Now I am tinking to go to Turkey, Bulgaria. If you have some imformations about these countries, please tell me. ...
無関心と憎しみの連鎖の中、想像力は失われていく
深夜にマケドニアという非常にマニアックな国に着いた。手元のロンリープラネットによると、マザーテレサの生まれた国らしい。これから、コソボ行きのバスを探します。 実は小学生の時、非常にマセていた私は夏休みの自由研究で旧ユーゴの内戦について調べ発表した。 そういうわけで、ここもそれなりに思い入れのある場所だ。 さて、イスラエル・パレスチナを離れて二日がたった。 ガザの侵攻で21名が死んだことを、先ほどホテルで流れていたBBCを見て知った。 現地にいるとき、ラマンラ近くで毎週行われているデモを二回見学した。 デモはパレスチナ人が中心となって行われていたのだが...
...一年の月日が流れて
ブカレストのネットカフェより更新。先ほどルーマニアに戻ってきた。 この後はコソボに行き、現地にすむ知人に会うつもり。 今回のイスラエル・パレスチナ訪問ではトルカレムでファタハ系のある軍事部門の幹部と4時間ぐらいインタビューしたり、ガリラヤ湖で泳いだり、ラマラ近くのある村でのデモに参加したりと、本当に充実していた。今も書きたいことが多すぎてまとまらない。 でも何よりうれしかったのは、去年の会議の参加者たちと、一年ぶりの再会を果たしたことだった。 パレスチナ人参加者だったアクラムは、ラマンラの街に香水屋を二件、化粧品屋を一件オープンさせていた。得意のフランス語を...
...エルサレムより
中東来て一週間がたちました。 到着翌日はイスラエル軍が投げる催涙弾を初体験した。 あれはきつい。目からも鼻からも水があふれ出る。 昨日はジャーナリストのYさんの運転する車で、シリア・レバノン国境付近のドルーズ族の村に連れて行って頂いた。シリア国境を見て少し複雑な気分になったものの、もっぱらの話題はドルーズお姉様方についてだった。レバノン・シリアには、さぞかし美女が多いのだろうと、想像を掻き立てられた。 今日はJICAの方にジェリコの開発に関する会議につれてっていただいた。休憩中は、海抜マイナス300メートルの暑さの中、3月イスラエルが侵攻した刑務所跡を見た。ひどかった。 そんな...
...Declare myself
私はイスラエル・パレスチナに初めて入ったのは、ちょうど二年前。 本や人の受け売りではなく、自分の目で見て頭で考えて、自分の言葉で語ることが、あの経験を経てようやく少しだけできるようになった。 中東問題を一生かけて研究したいと今は思っていないけど、それでも私にとってあそこが大切な場所であることには変わりない。 アザーンの音色や無駄に多い車のクラクション、雲一つない空と砂煙、エルサレム旧市街の混沌、テルアビブの夕日、思い出すと胸が熱くなる。 (ついでにイスラエルの軍服美女と正統派ユダヤ人の揉み上げも) 英語も使えず役に立たないことが明白だった二年前の私を、現地に送り出してく...
...ブカレスト!!!
昨日ブカレストに到着。 はるばる電車で8時間。貧乏という病のため、鈍行列車の二等席を利用。暑く長かった。 ルーマニアは日本とそこまで物価が変わらない(物によるが)ため、生活が本当にきつい。しかし、昨日は奮発して1000円ぐらいでルーマニア家庭料理を食べた。ブカレスト記念だ。 ブカレストは日本並みに暑い。山奥の我が街では、ずっとシャツにジャケットという格好で済ませてきたのだが、ここではTシャツ一枚でも汗が吹き出してくる。 以前JETROのホームページで見つけたブカレストの日本語使用可能なネットカフェに緊急非難だ。 これからインターコンチネンタルホテルで髪をきってくる予定。JICAのホ...
...Maybe we are born to kiss each other, maybe we are born to love each other
二日連続のブログ更新。 先日、同僚に何枚かの写真を見せられた。 どの写真も標識やら旗やらが二つずつあるのだが、そのうち下一方は全て塗りつぶされている。 ルーマニア語標識、ルーマニア国旗だけがあり、ハンガリー語標識、ハンガリー国旗が塗りつぶされているのだ。 これは実際にある村で起こった「いたずら」だ。 私の住むトランシルバニア地方では、歴史的にハンガリーの支配下に長くあったこともあり、ハンガリー人が大多数を占める集落も多い。それが時に、民族対立を生む。 それでも少しずつ共生への試みが続いている。 例えば、私の住む街のベンチは全て赤く塗られている。 それは、赤という色がル...
...「周縁」として生きる
"they lost" 一昨日、パレスチナ人のある友人にメッセで話しかけられたのだが、当初意味が不明だった。 "who are they?" ワールドカップの日本チームのことだった。 4年前、私は一試合を除いて日本戦は全て競技場で見た。準決勝も決勝も競技場で見た。 仙台まで日本対トルコ戦を見に行った時だったと思う。 トルコ側の人間が日本側のファウルで倒れるたびに、隣の女性が騒いでいた。 「死ね!」「消えろ!」 その時から、急に「日本を応援すること」に冷めてしまった。この女性と同じ共同体に属するということに、恥ずかしさを...
...ルーマニアからエグゾダス
四日連続の更新。 ルーマニアから離れられるというのは、正直嬉しい。 今までは「試練」と思って乗り切ってきたけど、それも「日常」となると意義を感じなくなってくる。 未だに街中を歩くとよくからかわれる。先週の火曜日は特に最悪だった。 公園を歩いていたらいきなり私の正面に学生集団がやってきて、大笑いし始めた。殴ろうと思ったけど、「「平和」研究所職員が暴行で逮捕」とかルーマニアの新聞で報じられたらシャレにならないだろうと思って、歯をくいしばって無視した。 唯一のアジアからの友人だった台湾人の女の子も最悪だった。 彼女はアイセックで働いているのだが、そのイベントがシビウという街であるので行こ...
...