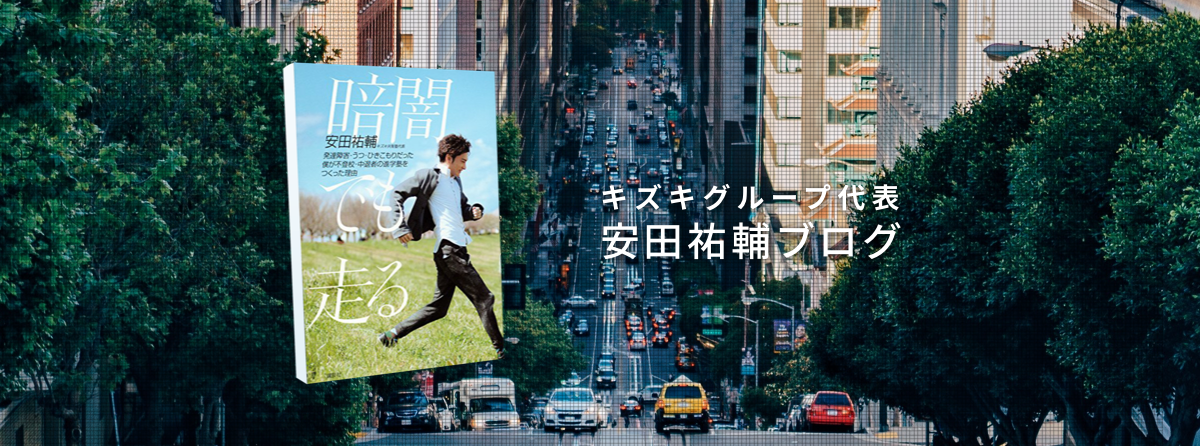学生時代を通じて、のべにしたら40カ国以上を廻ってきたけれども、日記をほとんどつけてはいなかった。 よくバックパッカーにありがちな、「俺はこの国のことを分かっています」的な態度が僕は好きではない。 けれども、今回は昨夏に北京で経験したことを書こうと思う。実はこの夏、再び中国に行くことになったので(雲南省だが)。 去年の夏にバングラデシュに行ったとき、途中北京とタイに立ち寄った。 どんな国でも「繁華街」と呼ばれているところには、おもしろいものが転がっているものなので、北京に到着すると「地球の歩き方」を片手に繁華街をうろうろした。 早速、一人の中年女性が近づいてきた。 「○△×○△...
...忘備録(2008年5月5日/就職活動)
N○Kエンタープライズを除けば、結局メディアは受けなかった。 尊敬する友人たちが、N○Kや新聞社や通信社で働いていたり内定をもらっていたりして、憧れは勿論あった。 バングラデシュのドキュメンタリーに、この二年間ささげてきたわけで、憧れがないわけがない。 実際、就職活動の時はいくつかの会社にプレエントリーはした。説明会も予約をした。 でも自分にはぬぐいきれない違和感が残っていた。それは、僕がしたいのは「伝達」ではなくて「表現」だということだったように思う。 おそらくジャーナリズムというのは、読者が知りえない情報を正確に届けることを第一の使命としているのだけれども、それは僕の関心からだいぶそれ...
...ミャンマーにて
8月15日ぐらいのことだったと思う。 僕はミャンマーの首都ヤンゴンにいて、帰国の便に乗るために、ゲストハウスの前でタクシーを拾った。 ゲストハウスの従業員に空港までのタクシー料金の目安を聞いていて(ミャンマーのタクシーは交渉制)、それは確か5000チャットだったと思うのだけれども、僕の前に止まったタクシーの運転手は、「7000チャットだ。」と答えた。 僕が「5000チャットのはずだ。」と反論すると、「今日からガソリンが値上げされたんだ。」と彼は答えた。 観光客だから騙されているのだと思い、「他のタクシードライバーに聞いてみるよ。」と僕は彼に言った。 僕の周りにはすでに何台かのタクシーが集ま...
...ミャンマーに関する誤解
ミャンマーで反政府デモが発生し、日本人のジャーナリストも殺害された。 ちょうど二ヶ月前、僕はミャンマーにいたのだが、現地滞在中、日本人が誤解している部分に気づいたので簡単に記載する。(昨年度、大学にてミャンマー史を学んだこともあり、忘備録も兼ねて) 1、アウン・サン・スーチーも、少数民族の分離・独立には反対である。 ミャンマーの話になると、日本の所謂「知識人」は、こぞってアウン・サン・スーチーを絶賛し民主化のことばかり口にするが、軍事政権もアウン・サン・スーチーも、ビルマ連邦はBurma as a nation という認識を前提としている。 ビルマには135(政府公式発表)もの民族...
...GMAILが使えないミャンマー
ミャンマーのネット状況は、軍の規制下にある。 これは建前だけではなく、実際にフリーメールは使えないことが多い。 というわけで、Gmailが見たいのに使えない。 困った。...
Hips don’t lie
ネットサーフィンをしてたら、懐かしいものを見つけた。 http://musicbox.sonybmg.com/video/shakira/la_tortura ShakiraのHips don’t lieだ。 その頃東欧ではShakiraが大ブームで、ルーマニアでもブルガリアでもマケドニアでも、一日一回はどこかで耳にしていた。 どうにもならない挫折を抱えながら、コソボの夕日の前に立ち尽くしたとき、後ろに流れていたのはこの音だった。 考えてみたら、あれから一年だ。 ちょうど去年のゴールデンウィーク、僕は東欧行きの飛行機の中にいた。 期待なんてものはこれぽっちもなくて、...
...マレーシアで見た「共生」
去年の秋にバングラデシュに向かう途中、マレーシアでトランジットをして4日ほど滞在した。 空港を下りタクシーでクアラルンプールへ向かったが、僕らはクアラルンプールの喧騒には一日で厭きてしまい、その翌日にはバスで約三時間かけて、「クアラスランゴール」という場所を訪れていた。ガイドブックにも載らないような小さな町だけれども、蛍のきれいな川があると聞いたことがあった。 バスターミナル近くの小さなボロ宿に荷物を置くと、早速情報収集を始めた。近くの食堂に入ると、華僑系マレーシア人の店主が、「蛍ツアー」を勧めてきた。 この食堂は旅行代理店みたいなこともやっているみたいだ。 夜再び食堂に行...
...「表現」について
僕は小学生の時ずっとピアニストになろうと思っていた。 ピアノの練習をしない日なんて10年間で数日あるかないかだったと思う。 県のコンクール等でそれなりの成績も残せたし、それだけ真剣に取り組んでいた。 結局、中学入学で家を出たのをきっかけにピアノはやめてしまったけれども。 幼かった僕にとって、自分と家族、自分と社会といった関係性の中で生まれた負の感情を、表出できるのは音楽だけだった。 そして去年、本や写真、映画に囲まれた生活をおくってみて、僕はそういったものに生かされ続けていることに改めて気付いた。 エドワード・サイードと共にアラブ=イスラエル混成オーケストラを結成した、イス...
...ルーマニアで学んだこと
ルーマニア生活を経て学んだことの大きな一つに、「自分がどれだけ他者に支えられているか」ということがあった。 1人東欧の田舎町で孤独になった時、東京にいる愛すべき仲間たちにすごく会いたかった。 そして、そんなことを感じている自分にすごく驚いた。 最近は先輩達がすでに就職してたり、同年代の子たちも就職したり卒論や就活で忙しかったりで、後輩と遊ぶことが多い。 けれども、あるとき「安田君といると、安田君の考えが先に頭の中に入ってきて、自分の頭で考えられなくなる」と仲の良い後輩に言われてしまった。 他者の大切さに気付いていながら、他者を受け容れられていない自分がいた。 よく考...
...「何がしたいか」ではなく、「何ができるか」
ルーマニアにいた時、自分の無力さに気付いて、全てが虚しくなった。 幼児的全能感を打ち砕かれるのが、僕の場合、少し遅すぎたのかもしれない。 「世界からみれば、「僕」という存在に意味などない。」 そんな当たり前の事実を認めるには、少々時間がかかりすぎた。 いや、そもそもその「世界」の意味を過剰に捉えすぎていたのだ。 そんなこと、ニーチェさんが100年も昔に説いているのに。 だから、「何がしたいか」だけではなく「何ができるか」を問い続けようと思う。 たとえ世界それ自体には何の意味もなくとも、世界は美しくて、そこにかけがえのない一瞬があるということにもっと感謝したいと思う。 そこから少...
...