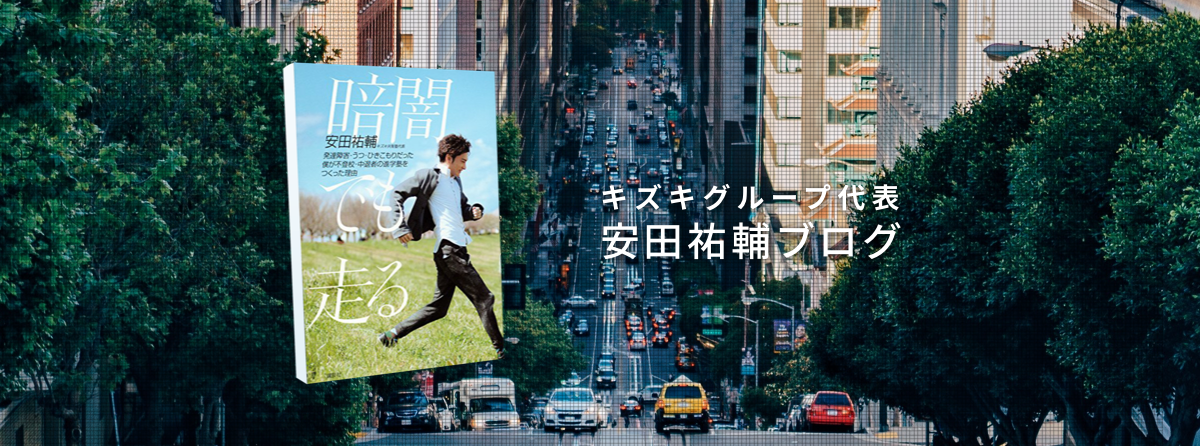「自己」というものほどわからない存在はなく、だからこそ社会学の対象となり続けたのであるし、80年代後半からは心理学の大きな対象ともなった。 そんなことを考えてる今日この頃(ブログを読めばおわかりのように・・・)であるが、そのテーマが今日の社会学の授業にも出てきた。 社会学者のルーマンは、「自分とは何であるか」という問いは近代社会特有の問題だと述べた。前近代社会では身分制度の中で、「自分が何者であるか」などという問いは生まれなかったのだ。 社会学者のギデンズは「自分とは何なのか」という問いは、何度も繰り返される答えのない問いだ(再帰性)と述べた。これは「自分とは何なのか」という問いに...
...「公共性」とは
ここ数年「公共性」について何かと問題となる。本来それは「人々の意見を聞き取る場所」「人々が議論する開かれた場所」のことだ。それがハンナ・アーレントやハーバマスが議論の対象としてきた「公共性」である。 ところがナショナリズムを巡る議論の中で、某小林氏などが使う「公共性」とは正反対の意味である。「公共」とは国家を意味してるわけではないし何かを勘違いしてるのかなんだかわからないけど、彼らが意味してるような「一つの方向のために意見・行動を集約する」というような意味ではない。 先週の社会学の授業で同内容が出てきた時は、なかなか興奮した。しかも来週の授業では「国民国家」についてやるらしいんだが...
...「テロの裏にある貧困」
ロンドンでテロが連続して起きたとき、テレビで「有識者」と目されているような人たちがこぞって言ってたのは、「テロの裏にある、貧困などに目を向けるべきだ」ということ。私は少々このような発言に懐疑的だ。 グローバリゼーションからくる貧困の問題もテロの裏にはあるだろうし、アルカイダがイスラム諸国の支持を受けているのは、間違いなく西側諸国への怒りがある。 しかし、この根本にある問題、特にアルカイダのようにテロに走る人間を形作るのは「宗教」であると言わざるをえない。「イスラム」というより、「イスラム原理主義」つまり「ワッハーブ」の問題が横たわっているのは間違いない。「イスラームを信じない者には何をして...
...パレスチナで生きるということ。
パレスチナ人の友人の従兄弟が、先日のイスラエル軍の攻撃で亡くなった。彼とは昨年の夏にパレスチナのラマラで行われたパーティーで知り合い、今年の春偶然ラマラのArab bank前で偶然の再会を果たした。そして2週間後,私の団体のイベントで彼を招致する予定である。 そんな彼はいまでもイスラエル人との「対話」を望んでいるのだろうか。そんな彼に僕は何ができるのだろうか。どんな言葉をかけるべきなのだろうか。 あまりに生きている「現実」が違いすぎる。どこまで僕の想像力が働くのかはわからないけれど、それでも心の底から思う。 こんな争い、もうとっとと終わらせて欲しい。 ...
NGO等の市民運動に対する考察
前にちょっとブログに書いたが、NGOとかそういったものを「自己満足」とか「偽善」そういった形で考える人がいる。まぁ私が代表を務めている団体に関しては、今のところはそういった位置づけが正しいかもしれない。(そうならないように努力中)しかし、それは現代社会を考える上であまり賢くない議論だ。 いわゆる「貧しかった」時代の市民運動とは、活動を行う主体は「弱者」という意識、つまり強者によって抑圧されている「弱者」からの視点である。40年前の学生運動などはその典型であろう。 ところが近代成熟社会の市民活動とは、それとは正反対の視点に立って行われる。すなわち、自らを「強者」とする視点だ。フェアトレードに...
...テロと国民としての責任
ロンドンでテロが起きた。多くの人が死んだ。「アルカイダ」の疑いが濃厚らしい。 何故かあまり知られていないけれども、このアルカイダの根底にある思想はイスラム教のワッハーブ派である。このワッハーブ派はクルアーンの都合のよいところだけを取り出し、一定の傾向をもつ解釈を行うことに始まり、他の全ての宗教を否定し、他の宗教を信じるものを認めない。 サウジアラビアという国はこのワッハーブ派の教義に基づき統治されている。 9.11の後、サウジアラビアのワッハーブ教の長老が出したファトハー(ムフティー(イスラーム法学の権威者)によって出される宗教的命令)の内容の一部をここで抜粋したい。 ...
...将来について悩むこと
最近悩むのは将来のこと。内定が出始めたK嬢や、F氏の商社マン姿を拝見し、院進学に向けた勉強で忙しいN氏や細君の姿を目の当たりにしたりする日々の中で、色々悩むところは大きい。 大学入ったころは「学者」を夢見てたわけであるが、学問は向かないとあきらめた。しかも、相変わらず将来的には世界平和を創るような職業を目指しているわけですが、研究対象として興味があるのは「日本社会」のことで(例えば戦後の新興宗教とか教育論とか)、国際関係論とかの本を読んでいると眠くなる。国際政治学者なんてものには一生縁がないであろうことを最近悟った。 それに学問では自分のプレゼンスが発揮できないことにも気付いた。N氏の情報によ...
...過去と未来を両手に抱えて
とりあえず、ブログの更新をサボりすぎた。ちょっと前に下書きとして書いてあったブログをアップします。最近結構病んでます笑 時が経つのは余りに早く、あれから一年の月日が流れた。過去を捨て去り未来への一歩を踏み出した瞬間だと思っていた。しかし僕の予想するよりはるかに奥に、記憶は沈着していた。それはここのところ少しショッキングな出来事が重なり、気付いたこと。 春の中東旅行の時、某大使館の人の家に泊まらせて頂いた。そして朝まで飲み明かした。その時、彼が述べた印象的な言葉がある。 「心に何か深い傷を抱えているような人間が、それを癒すかのように紛争とか貧困に興味を持つものなのかもしれない」 彼自身、その...
...イラク
今日、リングの合宿から帰ってきました。まぁ後々内容は書くとして、イラク人がうちに来た時の話を書こうと思う。 イラクから来たZaidは土曜日の夜、我が家にRingのT氏とともにやって来た。日曜日はY嬢とS氏という、パレスチナに一緒に行く予定となっているメンバーとともに、Zaidと東京観光をした。東京駅で待ち合わせ、皇居観光→靖国神社→市ヶ谷駅→御徒町→アメ横→上野駅というルートをたどった。Y嬢は家に帰り、夜はN氏が来て、S氏と共に始発で帰った。 初日、T氏とZaidと僕とでイラク戦争について議論となった。 Zaid曰く、「イラク戦争は正しかった」と。「サダムregiumを崩壊させてくれたブッ...
...僕の知るパレスチナ
月曜日、放課後Y嬢とリング用の原稿についてアドバイス。たまたま当団体メンバーのI嬢が通ったので、夜にあったJVCのパレスチナの活動報告会にさそう。エッセイのdueが延びたので行けるとのこと。上野のJVCの事務所に向かう。 パレスチナで子供の支援をしていた女性の活動報告を聞く。懐かしい写真もでてきた。ラマンラの中心街、カランディアの検問所、壁、あの場所で出会った人たちを思い出し胸が熱くなった。僕はパレスチナで、そこで生きる人の日常を見た。人懐っこい彼らとのやりとりを思い出すと彼らが僕にとって「他人」ではなくなる。どこか空虚に感じていた「中東和平」というスローガンが、現実味を帯びた瞬間であった。 ...
...