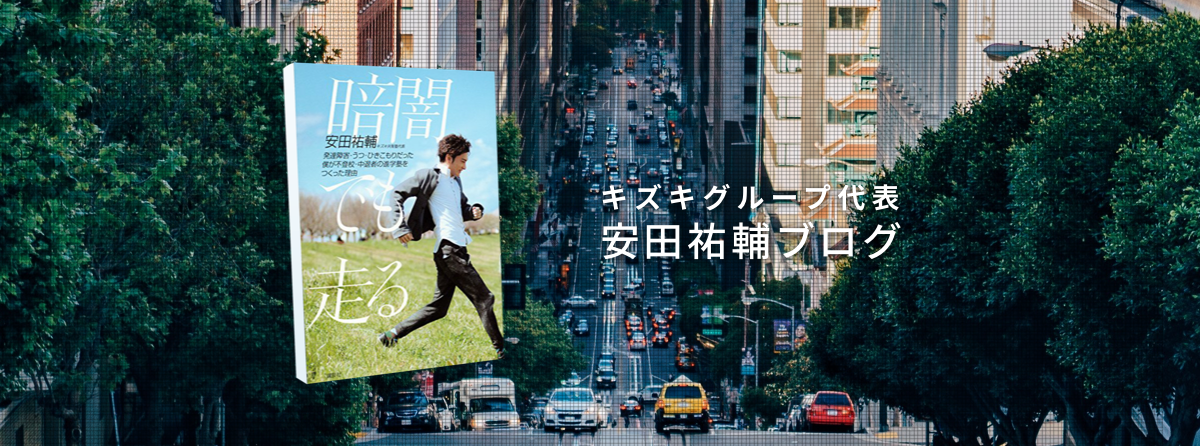"they lost" 一昨日、パレスチナ人のある友人にメッセで話しかけられたのだが、当初意味が不明だった。 "who are they?" ワールドカップの日本チームのことだった。 4年前、私は一試合を除いて日本戦は全て競技場で見た。準決勝も決勝も競技場で見た。 仙台まで日本対トルコ戦を見に行った時だったと思う。 トルコ側の人間が日本側のファウルで倒れるたびに、隣の女性が騒いでいた。 「死ね!」「消えろ!」 その時から、急に「日本を応援すること」に冷めてしまった。この女性と同じ共同体に属するということに、恥ずかしさを...
...自分がありたい姿について
もう一年も前の話になってしまうのだけれど、イスラエル人・パレスチナ人との間に対話の機会を創出し、そして日本社会にイスラエル・パレスチナに生きる人々の姿を伝えていくという活動を通して、色々考えさせられたことがあった。 事業規模が大きかったため色々な企業、財団、自治体、また多くの一般市民の方々に多大な協力を頂いたのだけれども、何度か「国際協力」そのものに対して批判を何度かうけたことがあった。 「イスラエル・パレスチナなんて私たちには関係ないだろ。」 内容面での甘さを批判されるのは構わない。むしろ、お願いしたいぐらいだった。 でも、世界で起こっている貧困や紛争を「関係がない」とかたづ...
...ナショナリズムについてルーマニアで考えた
私の住むトランシルバニア地方は人口の30パーセントをハンガリー人が占める。 ハンガリーの支配下にあった時期が長かったからだ。 先週、同僚に連れられて行ったハンガリー系のバーで、近くの大学で写真を学ぶ若者と話していたとき、ふいにナショナリズムの話になった。 「お前には分からないかもしれないけど、俺はどこまでいってもルーマニア人ではないんだ。」 彼は言った。 次の日、同僚のエルッド(ハンガリー系ルーマニア人)に、彼のアイデンティティーについて質問してみた。 「俺は愛国心とか民族意識だとか、そういうものが嫌いだ。」 きつい言葉で彼が言ったあとに、微笑んだ。 「俺はこのクルージュの街が好きさ。それで...
...「共同体」「国家」 partⅠ
私は基本的に「共同体」なるものに興味がない。 幼い頃から一番小さな共同体の単位である「家族」というものにも、あまり興味はなかった。だから小学校を卒業して、家を出た。 というよりも、最も信頼のおける共同体であるはずの「家族」さえ、私にとっては信頼できるものではなかった。だから「共同体」というものを信じられなくなったのだと思う。 「国家とはアプリオリな存在なのか」という問いは、在日二世である東大教授の姜尚中から発せられるから意味を持つのかもしれないが、竹島が問題になっても「あれは日本の領土だ」と噴きあがる気にもなれず、中国やインドの台頭が連日報道されたところで危機感を持つことも...
...近代社会における代替可能性について
近代社会とは機能主義に象徴される。 機能主義とは、機能を重視し、その機能を満たすためなら何でもいいという具合に、入れ替え可能性を推奨する。よく宮台の本に出てくる議論だ。 世の中全ては入れ替え可能となってしまう中で、あえて入れ替え可能ではない存在を求めているのが、今の私だ。 これは、恋愛についても当てはまる。 高校時代、様々な女性と付き合った。容姿のレベルがかなり高い女性もいた。 でも合わなかった。 容姿だけじゃダメなんだと思った。 学問とかNGOとかに興味のある子がいいと思った。 大学に入って、何人かの女性と付き合った。中には学問的な話ができる子もいた。 でも合わな...
...世界は多様で美しい
この二年間、色々なものを見て、色々なものを感じてきた。 その結果、何か行動をおこしたいと願い、微々たるものではあるが実際に形にしてきた。 ヘーゲルによれば、人間が他者に対して善き行いをするのは、「人間が常に他者の承認を必要とする」からだという。 NGO、NPOの盛り上がりの背景には、私たちがただ乗りしている社会システムの裏で苦しんでいる他者を見捨てることが正しい生き方だとは思わないという動機づけがあると、宮台真司はいう。 学問的な理論に基づいて色々と説明はできる。 ただ、私にとって行動の動機は「感情」だった。 9.11からアフガン空爆、イラク戦争、動いという流れ...
...かけがえのない自己とは
「この世からきれいに消えたい」 藤井誠二・宮台真司共著 去年読んだ中で最もおもしろかった本だ。 私が所属していた某学生団体の一部のメンバーの中でも、密かなブームが起こっている。 それに関連して、昔考えてたことを書く。 高校時代、私はかなりの数の女性と付き合った。高校一年生の時だけで二桁は超えた。 今から考えてみると、人間の思考パターンを知りたかったのだと思う。 「こういう家庭環境に育ったから、こういう性格なのだ。」 「私がこういう行動に出れば、彼女はこういう行動に出る。」 どこにも居場所がなく世界を悲観的にみていた当時の私は、全てを実験と捉えていた。 そしてその結...
...意味と強度
まず始めに、そろそろこのブログを撤退したいと思う。あまりに多くの人に公開しすぎた。 MIXIやGREEにつなぐかはまだ悩みどころだけれど、とりあえず近いうちにブログを変えます。 さて新年だった。 家にホテルのカウントダウンパーティーのチケットが余っていたので、友人を誘って行った。 食事も豪華だったし、バンド演奏も良かった。 その後はホテルが手配したバスに乗り、浅草寺へ。初詣の後は、高尾山で初日の出を鑑賞(曇ってて見えなかったが)。 実は初詣など8年ぶりぐらいだった。 中学生の頃から、私はキリストの誕生日を祝った後に神道の儀式を行うという、宗教的な鈍感さがいやだった。私は無宗教だし、クリ...
...世界はそんなに単純じゃない(1)
長くなりそうなので、何回かに分けて書く予定。 この文章をこの一年ぐらい考えてきたことの総括としたいなと思っている。 私が団体をやっていたとき(引退まで後一ヶ月)にいつも悩まされていたことがある。それは「この活動がイスラエル・パレスチナの和平に繋がるんです」という台詞が言えないということ。 イスラエルの人口は約700万、パレスチナは難民を含めたら約500万。12人呼んで何とかなるほど情勢は単純じゃないし、だからこそ私は夏会議中、スピーチの時はいつも言葉に詰まった。私は自分の考えを短く表現する言葉を持たなかったからだ。(もちろん個人レベルで時間をかけて話を伝えることならできた)...
...今、問題意識の対象となっているもの
最近問題意識の対象となっているものが大きく分けて二点ほどある。 一つ目がキリスト教原理主義とナショナリズムとの関係。 日本のキリスト教原理主義方々は、妙な愛国心を持っている方が多いと感じる。 イスラエルに強い宗教的な目的で行く方々、「イスラエルには行くがパレスチナには入らない」ような方々は、往々にして愛国心が強い。聞いてもないのに靖国神社に対する肯定的発言をアピールしてくる。 今までその手の方々にたくさんお会いしてきた。 また日本のキリスト教の某一派は、「新しい歴史教科書を作る会」の熱烈なサポーターだったりする。 両者には思想的な繋がりがあるのだと思う。 私の問題意識の中に「宗...
...