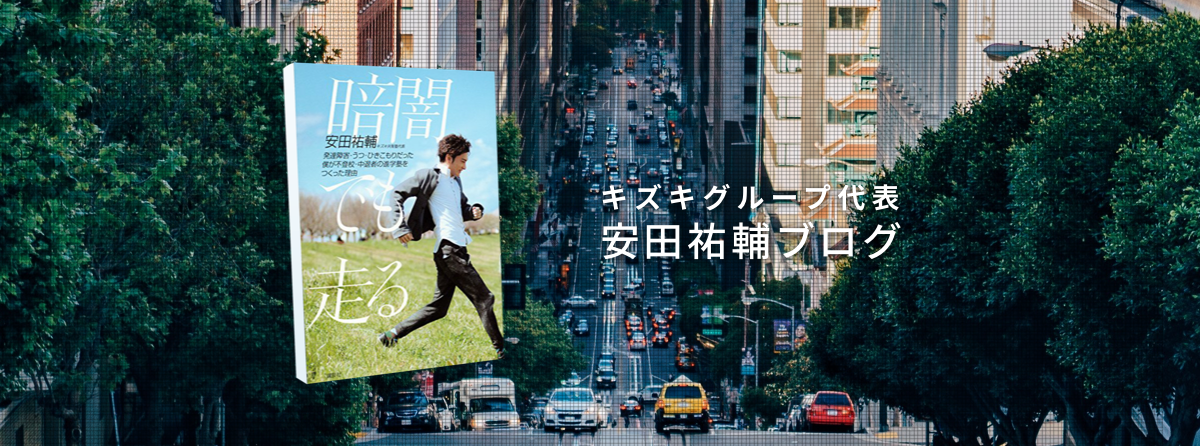二年前、とある学生団体に頼まれて、イラクの大学生をうちに泊めたことがあった。 国際関係論を専攻しようと思っていた当時の僕は、当然のことながらイラク戦争の是非を彼に問うた。 幼かった当時の僕は、彼からの答えに、「アメリカ非難」を期待していた。 けれども彼は僕の予想に反して、「隣国からのテロリストからイラクを守っている」とアメリカに対する感謝を述べた。 海外経験も少なく、物事を多面的に捉えることができなかった当時の僕は、本当に戸惑った。 戦争に反対して本の中で、テレビの中で熱弁を振るう「知識人」たちや、各地で行われた自己満足的なデモ行進を思い出した。 爆撃下で苦しんだイラク人が...
...「諦念」としての愛国心
バングラデシュ滞在の後半では、ルマさんのお兄さんに再会した。 「国境や民族なんて、なくなってしまえばいいのに」 春会った時にいわれたセリフを、僕はずっと覚えていた。 http://yasudayusuke.spaces.live.com/blog/cns!14ECB3DBFA167A80!942.entry?_c=BlogPart その日、彼との会話が深夜までに及ぶと、「もう寝たほうがいいかな?」と気を使ってくれ、後輩たち(女性)がシャワーを浴び終わるとドライヤーを持ってきてくれた。その気遣いは「バングラデシュ人」にはないものだった。 もちろん彼の見た目はどこから見てもベンガル人だ。そ...
...違う「世界」に生きているということ
昨日まで後輩と共に、大阪の釜ヶ崎にいた。 東京から夜行列車と鈍行列車に揺られること9時間、釜ヶ崎のある新今宮の駅に降りた。 駅を降りると正面に見えたのは、職安だった。 その横の通りには、路上マーケットが開かれていて、電気機器、洋服、アダルトビデオなどがブルーシートの上におかれている。 昼間からワンカップ大関を片手に路上に座り込む者、ゴミを漁る者、その数の多さに驚いた。 まず、宿を探した。 「ドヤ」と呼ばれる一泊800円程度の簡易宿泊所が立ち並ぶ。 仕事があってお金があるとき、労働者たちはこの宿に泊まるのだろう。 僕たちは、大通りに面した一泊1000円程度の宿にチェックインした。...
...弱くある者たちへ
年末は山谷に通っている。 実は、今私が住んでいる場所から自転車で10分のところにあるのだ。 山谷とは日雇い労働者が集まる、東京南千住近くの街だ。 一泊2000円程度の簡易宿泊所が立ち並び、アルコール依存症の中年男性たちが、ふらふらと歩く。 夜になると近くの商店街では、下りたシャッターの前にホームレスの男性たちが毛布を被って横になる。 少し離れた隅田川沿いにはブルーシートに覆われた「小屋」が並び、ホームレスたちの日常が営まれている。 先日は、ホームレスの方々の自立支援をしているNPOの活動に参加した。 隅田川沿いの「小屋」を一軒一軒訪ね、名前、年齢、収入、体調などを聞き歩く。 ...
...世界へのかかわり方
先週あるソーシャルベンチャーのパーティに参加して、自分の姿勢がいかに中途半端かを思い知らされた。 何かが「問題だ」と感じたら、そこから真摯に行動し続けること、そんな大切なことをこの一年間忘れていた気がした。 この三年間イスラエル・パレスチナの問題に関わり、アジア・中東を旅し、ルーマニアで働き、世界を見て感じてきた。 その中で何をすべきなのか、自分なりに問い続けたつもりだ。 今も、映画を撮り始めたり、写真を始めたり、NPOの理事をやったり、それなりに色々手は出している。 けれども、全てが中途半端なのだ。 そんな悩みをパーティで隣にいた後輩に愚痴っていたところ、 「今...
...It is not half so important to know as to feel.
"It is not half so important to know as to feel" (知ることは感じることの半分も重要ではない) -レイチェル・カーソン 「センス・オブ・ワンダー」より 高校生の時ぐらいまで、僕は世界が全て敵だと思っていた。 親も友人もいないようなものだったし、それでいいと思っていた。 でも、18歳の時、テレビや新聞で報道される世界の紛争や貧困を見て、「何かをしなければ」と思った。 不条理な環境で生きてきて、感受性が鋭くなりすぎていた。 最近になって思うのだけれども、あの時の僕は...
...「異常」と「正常」の境界
うつ病の具合はだいぶよくなった。 通院の必要もとりあえずなくなった。 私の通っていた精神科には、いつも変わった人が多かった。 自分の鞄に落書きを続ける女子高生、受付の女性にどうでもいいことを話し続ける若い男性、数えればキリがない。 今までは彼らが「異常」で、「正常」な私と住む世界には境界があると思っていた。 でもちょっとしたことをきっかけに、私も「異常」の仲間入りをした。 「異常」であることを、理解できるようになってしまった。 ようやく気付いたことだけれども、「異常」と「正常」の壁は、すごく薄いのだ。 「異常」な世界に入るために、複雑な手続きはいらない。 犯罪にしたって...
...共に生きるということ
「ぼくは子どもの頃からずっとひとりで生きてきたようなものだった。・・・しかし大学生の時その友達に出会って、それからは少し違う考え方をできるようになった。長い間1人でものを考えていると、結局のところひとりぶんの考え方しかできなくなるんだということが、ぼくにもわかってきた。1人ぼっちであるというのは、ときとして、ものすごくさびしいことなんだって思うようになった。」(村上春樹 「スプートニクの恋人」より) 9月の前半、アメリカのパレスチナ人・ユダヤ人のピースキャンプに呼ばれていたのだが、仕事が始まる前の二日間僕はサンフランシスコ近郊に滞在していた。 現地のキャンプオーガナイザーが手配して...
...弱さを認めるということ
二日連続のブログ更新。 ****** 今マケドニアのオヒリドなるリゾート地にいる。 一人で過ごすリゾート地など、何の楽しみもない。 なので今日の夜行バスでブルガリアのソフィアにいきます。 ソフィアでブルガリア美女たちを戯れたいところだけど、そんな金はまったくない。 早く物価の安いトルコに入らないと、資金がつきる。 荷物を詰めたりで一度ルーマニアには戻らないといけないけど、研究所には戻らないことにした。 ****** 研究所にいたとき、周りはルーマニア人とアメリカ人・オーストラリア人だけだった。 いつも言語的に取り残されていて、つらかった。 街を歩いているとき周りから差別的な行動をとられるたびに...
...Maybe we are born to kiss each other, maybe we are born to love each other
二日連続のブログ更新。 先日、同僚に何枚かの写真を見せられた。 どの写真も標識やら旗やらが二つずつあるのだが、そのうち下一方は全て塗りつぶされている。 ルーマニア語標識、ルーマニア国旗だけがあり、ハンガリー語標識、ハンガリー国旗が塗りつぶされているのだ。 これは実際にある村で起こった「いたずら」だ。 私の住むトランシルバニア地方では、歴史的にハンガリーの支配下に長くあったこともあり、ハンガリー人が大多数を占める集落も多い。それが時に、民族対立を生む。 それでも少しずつ共生への試みが続いている。 例えば、私の住む街のベンチは全て赤く塗られている。 それは、赤という色がル...
...