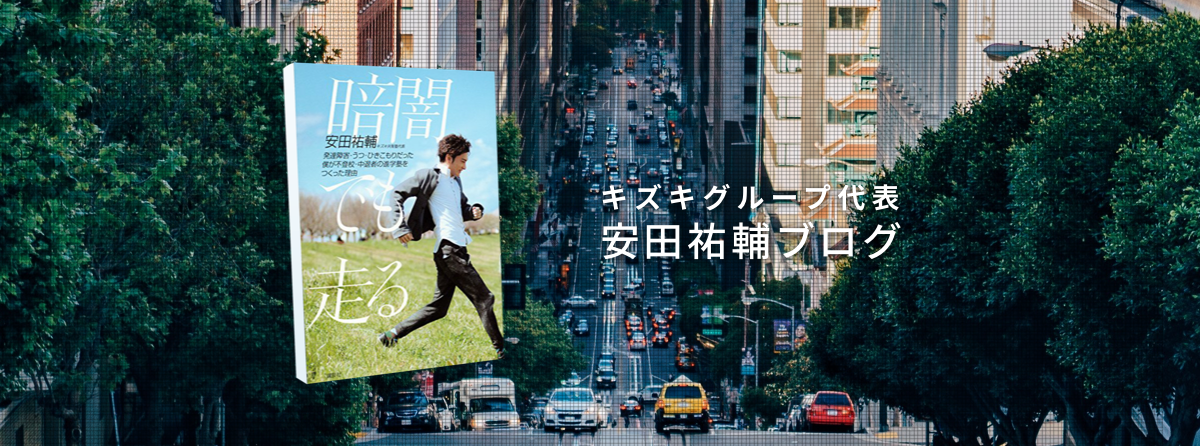忘年会シーズンがやってきた。昔の友人たちと会うことが多くなった。 あの頃は本当に楽しかったと思う。 自分が生きている世界が全てで、その中でただひたすらもがいていた。 髪を切った。 髪を黒くした。 ひげを剃った。 就職活動、である。 あの頃のように、熱くなれるもの(仕事)に出会いたい。...
独り言
先月24歳になった。 23歳の一年間は、本当につらかった。 23歳になる直前は日本にイスラエル・パレスチナ人を招致して、個人が動くことで社会が変わるんだって確信を持って、その後は新聞やテレビやラジオに出演したり、某学会に招かれて九州まで講演しに行ったりして、人に伝える意義を感じて、23歳になるとルーマニアに行って挫折して、でもそこから帰国してすぐに某NGOに招かれてアメリカに行っていた。 常に自分が前進している実感があって、その先の未来を信じていた。いつも何かを感じて、何かを学んでいた。 23歳の一年間は映画を作ったりはしていたけれども、とくに何かをしていたわけではなかった。小...
...自己実現なんていらない
僕が見るニュースは、神保哲夫さん(実は大学の先輩でもある)のビデオニュース・ドットコム(http://www.videonews.com/)ぐらいなんだけれども、その先日の特集がおもしろかった。派遣労働でなんとか食いつなぐ現代の「貧困」者についての特集だ。 一度「貧困」に陥ってしまった結果、「自分自身からの排除」という現象が発生し、貧困に陥ってしまった自己に対する信頼が低下してしまう。それが、この「貧困」の大きな問題である。彼らが抱えている問題は、単に金銭的な貧困ではなく、自己嫌悪という精神的な問題なのだ。これに対して宮台が述べていたのは、「努力して成功した人も、努力して失敗した人も、...
...夢に生きて、死ぬ
僕は高校のころ、本当に頭が悪かった(今以上に) テストの点数は基本的に一桁だった。選択肢の問題しか、正解できないのだ。 特に高二から高三にあがるときは、大変だった。成績が赤ばかりで、かなりの数の科目で追試やら補修やらを受けることになった。 数学の追試の前日、教師が僕に言った。 「追試は期末テストと同じ問題を出してやるから、暗記してこい。」 頑張って暗記したけれども、70点が関の山だった。 高校を卒業して大学受験の勉強をしてから、あの時の曲線のグラフが「微分積分」と呼ばれるものだと知った。 高校の頃から本当にお金がなかったので、バイトはかかせなかった。 ファーストフードの厨房、レスト...
...自由でありたい
中学、高校と社会の底辺に近いところで生きてきた僕にとって、大学に入ってからの生活は新鮮そのものだった。 高校の頃は、「どこの暴走族が強いか」とか「今日はどこにナンパに行くか」とか、そんなことしか友人との話題にのぼらなかった。学校には三日に一日行く程度だったし、その一日も授業中は同じ場所に座っていることができずに、気づくとトイレで煙草を吸っていた。 だから大学に入学したときは、別の世界に迷い込んだような気がしていた。大学に入ってから出会った人々は、僕がそれまでいた世界とは異次元に住む人たちであったからだ。 僕には別の世界に行く「自由」があったのだ。 去年ルーマニアでの挫折から感じたこ...
...社会起業と構造主義
ソシュールを元祖とする構造主義が明らかにしたことは、「私」一人一人の思考が常に言語・文化といった「構造」に規定されており、その枠組みの中でしか「私」は生きられないということだった。 ビジネスと社会貢献を結びつける「社会起業」というパラドックスは、「資本主義」という現在の社会構造に依拠しているという点で、既存のNGO・NPOとは異なる。「私」が生きる社会の外側に理想を追い求めるのではなく、既存の枠組みの中で社会を変革していこうとする姿勢が、古いようで新しい。 僕自身、学生NGOをやっていた頃は、「オタク集団」ではなく「今どきの普通の若者」が活動の主体であることが、社会の共感を得る鍵だ...
...とうとう直営店オープン!!
日本に帰国して次の日の朝から、仕事に復帰した。 そして、朝5時まで仕事をして朝9時に出社するような日々が一週間続いた。 家にはシャワーを浴びに帰るだけになった。 なぜかといえば、その帰国した次の週は東京入谷に会社の直営店がオープンする日だったからだ。 http://www.mother-house.jp/index.shtml ちょうど先週S新聞の一面で特集されたこともあって、当日はたくさんのお客様が来てくださった。 さらに、9月1日には東京ディズニーランド内のイクスピアリにも直営店がオープンし、9月19日には講談社から社長の自伝が発売される。本当に忙しくなるのはこれからだ。 ...
...長い旅の終わりに
ヤンゴンから古代都市バガンに向かう15時間のバス。夜7時ころ、日は沈み外は暗くなるが、バスの明かりはつかない。前方のうつりの悪いテレビで、ミャンマーのコメディらしきものがやっていて、時折乗客の笑い声が聞こえる。当然僕には、理解できない。何もすることがないので、目をつむり考えていた。「もう旅は終わりにしよう。」 ようやく気づいた。僕は、二年前の夏から何も掴んではいないし、このままじゃ何も掴むことができない。 この二年間で積み上げたもの、それは事実という名の経験だけだった。ルーマニアで働いたし、ITベンチャーでインターンもした。世界もあちこち回った。本も200冊以上は読んだし、映画も山のように見た...
...グローバリゼーションを「操縦」する
グローバリゼーションに抗するために、「国境を超えた市民の連帯」は謳われた時期があったが、その運動が実際に大きな力を持つには至らなかった。理念的に「正しい」行動であっても、それが実際に効果を上げるかは別問題なのだ。 (某学者の言葉を借りれば、「表出」と「表現」は異なるということだ。) グローバリゼーションに関して言えば、「抗する」のではなく「操縦する」という視点が必要だと、私は考えている。 つまり、今すでにある枠組みを壊すのではなく、その枠組みの中でできるだけ良い方向へと、舵をずらすような方法を探すことが重要なのだ。 だから、私は先進国と途上国を新しい角度から「つなぐ」ことで、山積...
...存在
バングラデシュから帰ってきてすぐに、大学、専門学校、会社が始まった。 平日週二回は朝から夜まで大学、週三回は夕方から夜まで専門学校、週三回朝から夕方まで会社、土曜日は会社もしくは専門学校の補講がある。 専門学校では芸術方面の人々と、ITベンチャーではビジネス方面の人々と知り合うことができた。 どちらも今まで余り交流することのなかった人たちだ。 だから、彼らから貪欲に学んでいきたい。 何かを感じたとき、そこにある不条理に立ち向かえる存在でありたい。 東京でも、イスラエル・パレスチナでも、そして今回のバングラデシュでも、僕は感じていた。 でも「力」が足りない。 だから、...
...