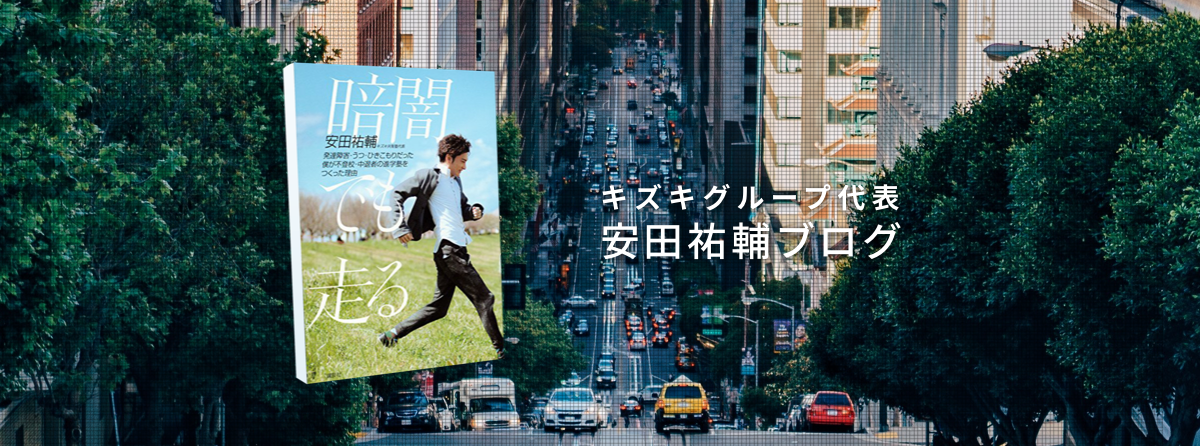一年半ほど前、ある女性からストーカーに近い行為を受けていたのだが、どうやら最近よく投稿されている意味不明なコメントがその女性からのものらしいということが分かった。ルーマニア生活で一杯一杯なのに、本当に迷惑な話だ。 というわけで自己紹介なしのコメントは即削除します。 あしからず。 ...
英語がきつい
今まで色々なところを旅してきて、特に夏以降英語をちゃんと勉強して、それなりに英語ができるようになった気がしていた。 しかし、それは気のせいだったみたいだ。 国連の明石康さんが言っていた。 「英語は下手でいいんです。」 そして確かに彼の英語は下手だった。私に妙な自信をくれた。 しかし、そんな自信はいらなかった。 少なくとも今まで旅した国々で、「英語が理解できない」ということはほとんどなかった。インドでもネパールでも、日本人「なのに」英語がうまいと褒められ、調子に乗っていた。 しかし、相手がネイティブスピーカーとなれば、事情は異なる。 一緒に仕事をしているアメリカ人の言ってる事が20%...
...ルーマニアより
とりあえず、今ルーマニアにいます。明日から仕事開始です。 私が担当するプログラムのうちの一つは"Peace Camp"です。下記のアドレスをご参照あれ。 http://www.patrir.ro/peacecamp/ 平和とか開発とか、様々な分野で活躍する世界の若者を約200名集め、"Peace Camp"を開きます。デッドラインはもう過ぎているのですが、まだアプライ可能だと思います。興味のある方は是非。 質問等は直接私に連絡ください。 では、こっちでの生活が落ち着き次第、色々ブログを書きます。...
ネパールの風景
ネパールで下院が復活し、再び民主主義の風が流れ始めている。 見覚えのある風景を新聞で発見するたびに、あの場所に生きる友人たちを思い出す。 一年前に某国際学生会議で知り合った友人、ナラヤンとは、この春ネパールで再会した。 「タイにしろ、日本にしろ、国王が尊敬される国は、国王が民主主義を尊重している。でもこの国の王は最悪だ。」「私達の国に民主主義はない。」 彼の家で彼の妹さんが作った料理をご馳走になっている時、彼は言った。 彼は国際NGOで働く非常に優秀な男なのだが、私のために一日半仕事を休み、興味を持っていたネパールの少女売買を防ぐためのNGO(http://www.mait...
...「共同体」「国家」 partⅠ
私は基本的に「共同体」なるものに興味がない。 幼い頃から一番小さな共同体の単位である「家族」というものにも、あまり興味はなかった。だから小学校を卒業して、家を出た。 というよりも、最も信頼のおける共同体であるはずの「家族」さえ、私にとっては信頼できるものではなかった。だから「共同体」というものを信じられなくなったのだと思う。 「国家とはアプリオリな存在なのか」という問いは、在日二世である東大教授の姜尚中から発せられるから意味を持つのかもしれないが、竹島が問題になっても「あれは日本の領土だ」と噴きあがる気にもなれず、中国やインドの台頭が連日報道されたところで危機感を持つことも...
...近況2
昨日に引き続き、近況を。 今日は朝、大使館に行きビザに関する質問をする。一応、疑問は解消される。 午後は航空券予約。 安さ重視ということで、台北経由ウィーン行きのオープンチケットを購入。ルーマニアの首都ブカレスト行きのオープンチケットは航空会社が限られていることもあり、20万以上・・・ というわけで、ブカレストにはウィーンから夜行列車で入ることになった。 そして出発日は5月5日。 この日までは、日本にいます。...
近況
東南アジアから戻ってきてから、毎日ひまにしている。 やるべきことは山積みなのだが、やるべきことを行える時間帯が限られているのだ。 ビザの準備、国際キャッシュカードの準備、国際免許の準備・・・ 全ての用事は夕方までで終わる。しかも休日には何も出来ない。 少々ビザの準備に手間取っているのだが、ビザの目処が立ち次第航空券をとる予定である。 おそらく五月頭に日本をたつことになるだろう。 さて、東南アジアにいるとき携帯を休止していたのだが、どうやらメールアドレスが元に戻せないようだ。 あしたドコモショップに行く予定ではあるが、私に何か連絡のある方はパソコンのメールか電話でお願いします。 ...
I have just come back to my home
今、家に着いた。 今日までの一ヵ月半、バングラデシュ、インド、ネパール、タイ、ラオスと旅してきた。 旅をしているうちに、所謂「観光地」にはほとんど行かなくなった。 新たな町に行くと、バイクを借りて何時間も走ってみる。 どんな大都市であってもバイクで少し走ってみれば、すぐにのどかな田園風景に変わる。 そしてふと見つけた茶屋に、バイクを降りて入ってみる。 その土地の匂いを感じ、その土地の人と出会い、時には一日中「どうでもいい」話を続ける。 別れ際には決まって、「今度はいつ来るんだ?三ヵ月後か?」との質問が待っている。 冗談で言ってるのかと思いきや、本人は至って真面目な顔だったりする...
...ラオスの貧困
今、ラオスにいます。昨日まで、ラオスの山奥にいたため、ネットが使えない状況にいました。 さて、ラオスに入ってもっとも驚いたことは、「物乞い」の姿をほとんど見ないことだ。タイのバーツ暴落から始まったアジアの通貨危機の時でさえ、食料的な貧困はほとんどなかったとされる。 ラオスのGNPは確か300ドル程度。世界の最貧国の部類に入る。それでは何が他の途上国と異なるのか。その鍵は「農業人口」にある。 私自身、多くの途上国で農村から都市への人口移動、都市での雇用の不足による「貧困」を目にしてきた。しかしこの国は、いまだ国民のほとんどが「農民」であり、都市労働者も未だに何らかの形で農村と繋がりを...
...南アジアのアイデンティティー事情
今から数時間後、カトマンズを発ちます。バングラ日記も書き終わってないわけですが、南アジアに生きる人々のアイデンティティーについて感じたことを少々。 バングラはムスリム国家なのだが、中東と比べるとだいぶ世俗的だと感じた。特に若者は、ムスリムというアイデンティティーよりも、「ベンガル人」としてのアイデンティティーの方が強いようだ。 中東の友人たちと話していると、会話の中にクルアーンやムハンマドの話がよく出てくるのだが、バングラの若者との会話ではベンガル地方に伝わる歌や食事、そして言語に関する話題が多かった。(年齢があがると少々状況が異なるようで、ホームステイさせて頂いた友人の家のご両親は非...
...